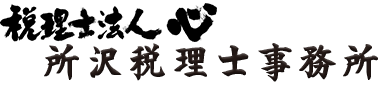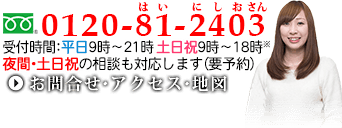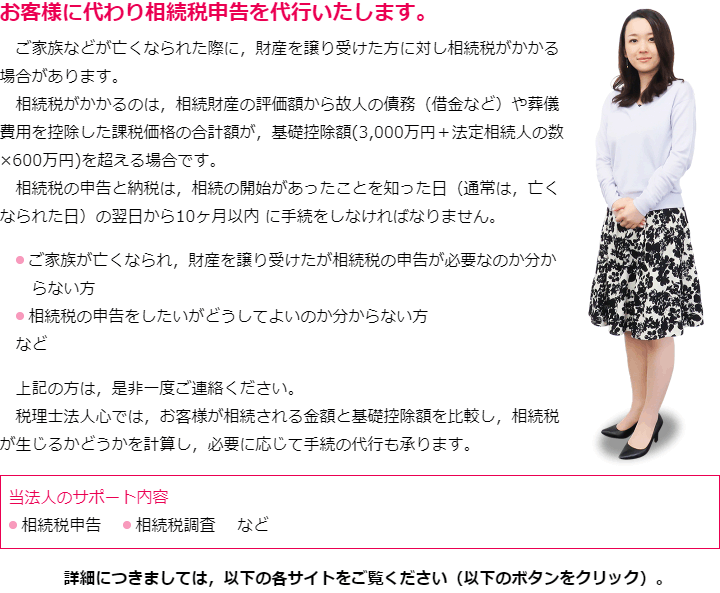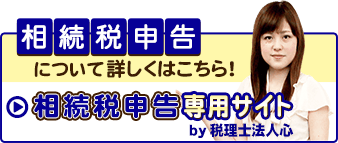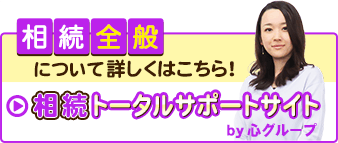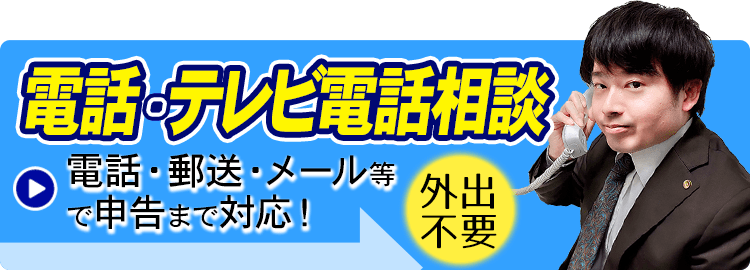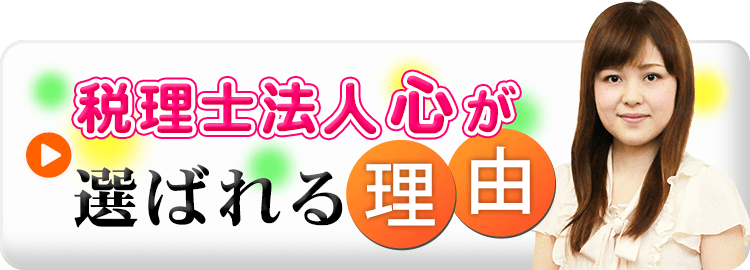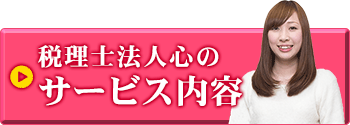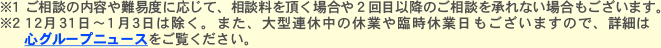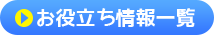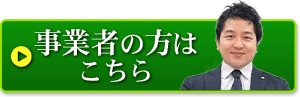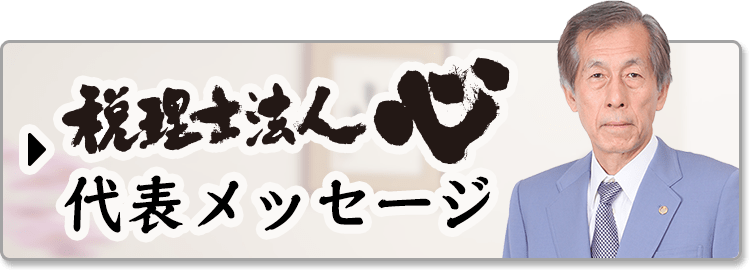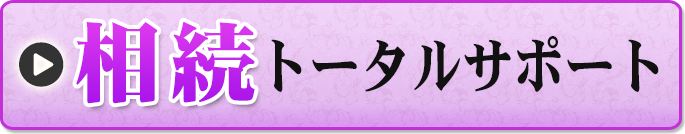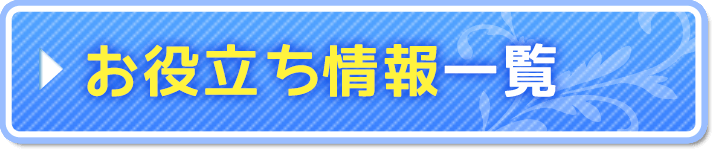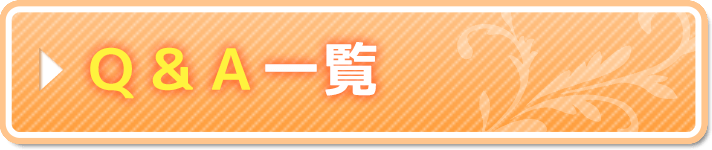相続税申告(相続発生後)
相続税申告が必要となるケース
1 相続税申告が必要となるケースの概要

相続税申告が必要となるケースとしては、まず課税価額の合計額が基礎控除額を上回る場合が挙げられます。
そのほか、相続税申告・納税額が0円であっても配偶者控除の適用を受ける場合や、課税価額の合計額が基礎控除額を下回っていても小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、相続税申告が必要となります。
国税庁のウェブサイトでは、簡易的に相続税の申告要否を判定することも可能です。
参考リンク:国税庁・相続税の申告要否判定コーナー
以下、相続税申告が必要となるケースについて、詳しく説明します。
2 課税価額の合計額が基礎控除額を上回る場合
相続財産およびみなし相続財産(死亡保険金など)の評価額の合計から、非課税財産の価額を控除し、相続開始3年以内(令和6年以降は7年以内)の生前贈与と相続時精算課税制度の対象となった財産の評価額を加算したものに、相続債務や葬儀費用の合計額を控除したものが課税価額です。
この課税価額が、次の式で求められる金額(基礎控除額)を下回る場合、原則として相続税申告は不要となります。
3000万円+600万円×(法定相続人の数)
なお、後述する小規模宅地等の特例の適用によって土地の評価額が下がる結果、課税価額が基礎控除額を下回る場合には、相続税申告が必要となります。
3 配偶者控除の適用を受ける場合
被相続人の配偶者においては、相続によって取得した財産(みなし相続財産含む)の評価額のうち、1億6000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税が課せられません。
そのため、例えば相続財産が全部で1億円分あり、そのすべてを配偶者が取得した場合には、相続税がかからないことになります。
しかし、配偶者控除の適用を受けるためには、遺産分割協議をしたうえで相続税申告が必要となります。
参考リンク:国税庁・配偶者の税額の軽減
4 小規模宅地等の特例の適用を受ける場合
小規模宅地等の特例を適用することができる場合、例えば被相続人のご自宅の敷地の評価額を最大80%下げることができます。
一般的に土地の評価額は高額なので、小規模宅地等の特例によって課税価額全体を大きく低減することができます。
相続財産の大半が被相続人のご自宅であった場合には、小規模宅地等の特例の適用によって課税価額が基礎控除額を下回るということもあります。
課税価額が基礎控除額を下回る場合であっても、小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、遺産分割協議を行ったうえで相続税申告が必要となります。